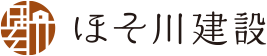坪庭
こんにちは、営業部の越田です。
今回は家づくりの提案の一つ「坪庭」について紹介させていただきます。
「坪庭」の言葉の始まりは平安時代の寝殿造りからと言われています。寝殿造は建物どうしが渡り廊下でつながれていて、その空間を「坪」と呼ばれるようになりました。また室町・鎌倉時代に寺院建築にも取り入れられ、禅宗の自然観「枯山水」もその流れからだそうです。
「坪庭」のある風景

では一般の生活の中に取り入れられたのには、どのような意味が考えられるでしょうか、そこは茶の湯の風土文化が大きく関係していました。京町家に象徴される「坪庭」は、桃山時代の「わび茶」茶室としてにぎやかな街の中で、田舎の風景を思わせる自然、わび茶に集中できる場として用いられてきました。
また、「小京都」と呼ばれ私たちが暮らすこの城下町もまた、文化と風土が深く関係してきました。城主が好んだ茶の湯と和菓の世界、職人を大切に伝統産業への寄与。その生活の工夫こそが、京町家のように間口が狭く奥に長い土地が多くそんな住環境で、自然の心地よさと安らぎを感じ、光と風通しを可能にした「坪庭」の世界観に必然性を追求したのかと思われます。
当社では、建築作品を通じて施主の暮らしに伝えたい「機能美」を表現できる空間として考え広く建築に取り入れています。例えば、外部の目線を気にせず気兼ねなく四季を楽しむ、青々と茂る葉で夏を感じ、紅葉の色付きで秋を感じるような四季の移ろいを生活に与えてくれます。また玄関先の淀みがちな空気の循環に活用させていただいています。さらに夜景では庭をほのかな照明で、ライティングすることで落ち着いた気持ちにさせてくれます。
そのような効果を考え、当社では「坪庭」を取り入れるデザインを今後も提案させていただきたいと考えています。